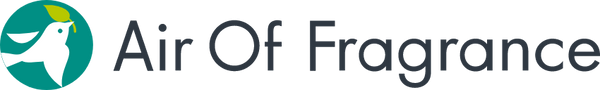桜の香りの正体とは? 塩漬けにすると香る“クマリン”の秘密とストレスが生む香りのメカニズム
Share
春の訪れとともに街を彩る桜。
そのやさしい香りは、実は桜が「ストレス」を受けたときに発するものだということをご存じですか?
先日開催した【チームムエット】でも、この不思議な“桜とストレス”の関係をテーマに香りを楽しみました。
今回は、桜の香りの正体「クマリン」と、それが生まれるメカニズムについて、「香りのサイエンス」としてご紹介します。
桜の香り=ストレスの香り?
実際に2025年4月1日に開催した、香りを言語化する体験プログラム「チームムエット」でも、春のテーマとして“桜”を取り上げました。
参加者の皆さんには「桜の花の塩漬けに由来する香り」「葉を揉んだ時にふわりと立つ香り」「桜餅を思わせる香り」などを表現していただき、
香りが記憶や体験とどうつながるのか、そしてその裏にある植物の生理的変化についても触れました。
この日の内容は以下よりご覧いただけます:
👉【チームムエット 2025年4月1日レポートはこちら】
香料としての桜、そしてAOFでの扱い
こうした知識を知ると「その香り、ぜひ自分でも嗅いでみたい!」と思われる方も多いかもしれません。
ですが実は、AOFでは現在“桜”に由来する天然香料を扱っていません。
その理由は、「本物の桜の香り」にこだわりたいため。
合成香料や単一のクマリン成分だけで構成された“桜風の香り”ではなく、自然に近い形で香りを届けるにはまだ時間がかかるのが現実です。
だからこそ、香りを知り、学ぶことから始める体験の価値があると考えています。
今回のように「なぜ香るのか?」を科学的に紐解いていく「香りのサイエンス」シリーズでは、今後も植物の香りの裏側にあるメカニズムを取り上げていきます。
まとめ
桜の香りは、春の象徴であり、やさしさや懐かしさを感じさせてくれる存在です。
しかしその香りは、植物がストレスを感じたときに発する“防御的な香り”=クマリンによって成り立っていることがわかっています。
香りは感性だけでなく、科学でひもとくこともできる――
「香りのサイエンス」シリーズでは、これからも香りの背景にある自然と知恵をご紹介していきます。
あなたの香り体験が、少しだけ深まるきっかけになりますように。